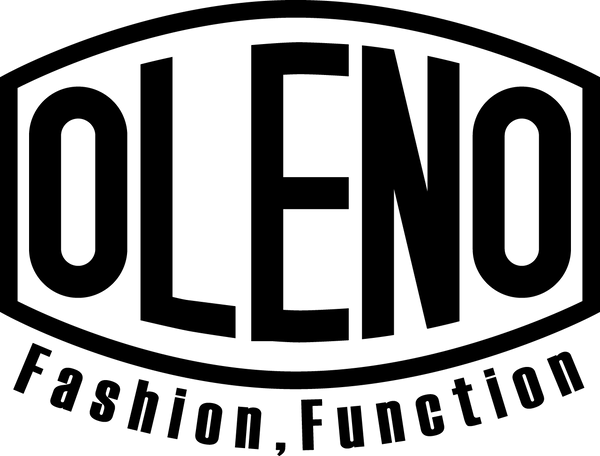Staff Blog

【2026年版】初心者も参加しやすい奈良県のトレイルレース全6選
初めまして、OLENOのひろきです。 我々OLENOの地元奈良県は、古都の歴史と自然が融合したトレイルランニングの宝庫です。世界遺産の若草山、生駒山系、ダイヤモンドトレイルなど、初心者でも走りやすいコースが充実しています。 本記事では、 ・距離25km以下 ・累積標高2000m以下 ・制限時間5時間以上 ・整備された登山道 ・公共交通機関アクセス良好の5条件を満たす、2026年開催の初心者向けトレイルレース6選をご紹介します。 2026年版 奈良県初心者向けトレイルレース全6選 1. 第23回 生駒トレイルラン<冬山> 冬の生駒山系を満喫できる人気大会。24kmのショートコースは初心者にも挑戦しやすい設定で、整備された登山道を走るため道迷いのリスクが低く安心です。 項目 詳細 開催場所 大阪府~奈良県 私市水辺プラザ(スタート&ゴール) 開催日時 2026年1月24日(土) 距離 ■24km:累積標高 約700m■29km:累積標高 約975m 募集定員 各300名 エントリー期限 ~2026年1月上旬 参加条件 健康な男女...
【2026年版】初心者も参加しやすい奈良県のトレイルレース全6選
初めまして、OLENOのひろきです。 我々OLENOの地元奈良県は、古都の歴史と自然が融合したトレイルランニングの宝庫です。世界遺産の若草山、生駒山系、ダイヤモンドトレイルなど、初心者でも走りや...

【2026年版】初心者も参加しやすい兵庫県のトレイルレース全6選
初めまして、OLENOスタッフの裕貴(ひろき)です。 兵庫県は六甲山系を中心に、都市部からのアクセスが良好なトレイルランニングの聖地です。 2026年版では、初心者向けの条件(距離25km以下、累積標高2000m以下、制限時間5時間以上、整備された登山道、公共交通機関アクセス良好)を満たす大会を6つ厳選しました。 【重要】兵庫県のトレイルレースは1月〜8月に集中開催されており、9月以降は初心者向けの大会が少ないです。本記事では、この傾向と対策も含めて詳しく解説します。 1. 第15回 六甲縦走トレイルラン2026 関西では有名な六甲山縦走路を走る人気大会。 神戸市街地から淡路島まで望める絶景ルートで、早春の六甲を満喫できます。須磨浦公園から宝塚まで、六甲山系の主要ピークを巡る関西屈指のトレイルレースとして知られています。 24kmのショートコースは初心者にも挑戦しやすい設定で、整備された登山道を走るため道迷いのリスクが低く安心です。 項目 詳細 開催場所 兵庫県神戸市 須磨浦公園(スタート)〜 宝塚(ゴール) 開催日時 2026年3月14日(土) 距離 ■24km:累積標高 約1,600m ■38km:累積標高 約2,000m 募集定員 500名 エントリー期限 ~2026年2月20日(金) 参加条件 20歳以上の健康な男女...
【2026年版】初心者も参加しやすい兵庫県のトレイルレース全6選
初めまして、OLENOスタッフの裕貴(ひろき)です。 兵庫県は六甲山系を中心に、都市部からのアクセスが良好なトレイルランニングの聖地です。 2026年版では、初心者向けの条件(距離25km以下、...

【2026年版】初心者も参加しやすい京都のトレイルレース5選
初めまして、OLENO新人スタッフの裕貴(ひろき)と言います。 以前、初心者も参加しやすい関西の初心者向けトレイルレースを紹介させていただきましたが、各地域のレース情報も欲しい!とリクエストをいただきましたので、京都のトレランレース(2026年版)のものをまとめさせていただきました。 2026年からトレランを始める方も、2025年あまりレースに出れなかった方もぜひチェックして出場してみてください! 1. 第4回 大文字100 DAIMONJI100 トレイルランニングレース 「最も都市部で開催される100kmのトレイルランニングレース」として、アクセスの良さが魅力のトレランレース。 12kmのループコースを周回する形式で、初心者でも自分のペースで挑戦しやすいレースです。初めての100km挑戦者を応援するアットホームな雰囲気で、サポート体制も充実している京都のトレイルレースとなります。 2026年は24kmコース(2周)が新設され、初心者でも参加しやすくなりました! 項目 詳細 開催場所 京都府京都市山科区(疏水公園スタート) 開催日時 2026年2月21日(土)〜22日(日) 距離 ■24km(12km×2周)【初心者向け新設!】■72km(12km×6周)■100km(12km×約8周) 募集定員 100名 エントリー期限 ~2026年1月31日(土) 参加条件 大会当日に18歳以上で、コースを迷わず完走できる自信がある方 大会詳細ページ https://go-trail.net/pages/大文字100 初心者にオススメな点:...
【2026年版】初心者も参加しやすい京都のトレイルレース5選
初めまして、OLENO新人スタッフの裕貴(ひろき)と言います。 以前、初心者も参加しやすい関西の初心者向けトレイルレースを紹介させていただきましたが、各地域のレース情報も欲しい!とリクエストをい...

【2026年版】初心者も参加しやすい大阪府のトレイルレース全8選
こんにちは、OLENOの裕貴(ひろき)です。 関西で行われるトレイルレースを紹介してきましたが、今回は大都市大阪で行われるトレイルレースについてご紹介させていただきます。 基本的には、初心者でも参加しやすいものを厳選しました。1月から11月まで、年間を通じて楽しめる大会をピックアップしていますので、トレラン初心者の方やトレランを始めようとしている方もぜひ参考にしてみてください。 【1月】第23回 生駒トレイルラン<冬山> 大阪府と奈良県にまたがる生駒山系の美しい自然を満喫できるトレランコース。大阪では最も身近な山でありながら、大阪平野を一望できる絶景スポットが多数あります。 なだらかなイメージですが、タフな部分もあり初心者からベテランまで楽しめるトレイルです。エイドステーションは29kmコースに4ヵ所、24kmコースに2ヵ所設置されており、手荷物預かりサービスもあります。 項目 詳細 開催場所 大阪府~奈良県(交野市スタート) 開催日時 2026年1月24日(土) 距離 ■29km:累積標高 約975m■24km:累積標高 約700m 募集人数 各300名 エントリー期限 ~2026年1月中旬 大会詳細情報 https://www.actrep-sports.com/ikoma-fuyuyama/ 初心者にオススメな点: 24kmコースは累積標高700mと初心者定義内。制限時間も5時間以上あり、ロード区間も2~3km含まれているため初心者でも完走しやすい設計。 大阪市内からのアクセスも良好で、京阪電車で気軽に参加できます。 【2月】かたのビッグロックトレイル2026 単なるトレイルランニングレースではなく、交野の里山を活用した「山のお祭り」をコンセプトとしたトレイルレース。...
【2026年版】初心者も参加しやすい大阪府のトレイルレース全8選
こんにちは、OLENOの裕貴(ひろき)です。 関西で行われるトレイルレースを紹介してきましたが、今回は大都市大阪で行われるトレイルレースについてご紹介させていただきます。 基本的には、初心者でも...

【2026年最新版】初心者も完走しやすいトレイルラン大会(北陸地方版)5選
北陸地方の豊かな自然を舞台に、初めてトレイルランニングに挑戦したい方に最適な大会が数多く開催されています。 日本海の絶景、立山連峰の眺望、越後の里山など、北陸ならではの魅力的なコースで、初心者でも安心して楽しめる大会を5つ厳選しました。 本記事では、2026年に開催予定または開催が見込まれる初心者向けの大会を、詳しくご紹介します。 初心者向けトレイルラン大会の定義 本記事では、以下の基準を「初心者向け」として定義しています。 【初心者向けの5つの基準】 ❶距離:25km以下平地のハーフマラソンを完走できる体力があれば挑戦可能な距離設定。トレイルはロードより負荷が高いため、まずは短めの距離から始めるのが安全です。 ❷累積標高:2,000m以下累積標高が低いほど、アップダウンが少なく体力的な負担が軽減されます。初心者には1,500m前後までが適切で、ハイキング経験があれば十分対応可能です。 ❸制限時間:5時間以上歩きを交えながらでも完走できる余裕のある制限時間設定。初めてのトレイルでは予想以上に時間がかかるため、ゆとりのある時間設定が重要です。 ❹コース整備:登山道が整備されている明確な道標があり、迷いにくい整備されたコース。初心者でも安心して走れる環境が整っています。 ❺アクセス:公共交通機関で行きやすい駅からのアクセスが良好、またはシャトルバスが運行されている大会。疲労後の移動も考慮した利便性が重要です。 これらの基準は、トレイルラン初心者が「完走の達成感」を味わいながら、安全に楽しめる環境を重視して設定しています。 北陸地方の初心者向けトレイルラン大会5選 1. トレイルランナーズカップ越後丘陵公園2026 開催日時: 2026年4月19日(日) 開催場所: 新潟県長岡市 国営越後丘陵公園 距離・累積標高: ロング12km(累積標高約600m、制限時間3時間)/ショート5km(累積標高約250m、制限時間2時間) 参加人数: 未公表 駐車場: 有(普通車2,155台、駐車料金320円) レースの特徴・魅力: プロトレイルランナー松永紘明プロデュースの常設トレイルランニングコース。整備された公園内の自然探勝路とトレイルランニングコースを組み合わせたコース設計で、春の新緑を楽しみながら走れます。 3歳から参加可能な親子向けのショート部門もあり、家族で楽しめる大会です。 初心者にオススメな点: 5kmのショート部門は3歳から参加可能で、制限時間2時間と余裕があります。未就学児は保護者の伴走が必須なので、親子で安心して楽しめます。 12kmのロング部門も累積標高600mと初心者に優しい設定で、ダブルエントリー(12km・5km両方参加)の割引制度もあります。 公式URL: https://trailrunners.jp/event/echigo-2026/...
【2026年最新版】初心者も完走しやすいトレイルラン大会(北陸地方版)5選
北陸地方の豊かな自然を舞台に、初めてトレイルランニングに挑戦したい方に最適な大会が数多く開催されています。 日本海の絶景、立山連峰の眺望、越後の里山など、北陸ならではの魅力的なコースで、初心者で...

【2026年最新版】初心者も完走しやすいトレイルラン大会(東海地方版) 6選
こんにちはOLENOです。 2026年、トレイルランニングに初めて挑戦したいけれど、「完走できるか不安」「どの大会を選べばいいかわからない」と悩んでいませんか? 東海地方には、初心者でも安心して楽しめるトレイルラン大会が数多く開催されています。本記事では、2026年に開催予定または開催が見込まれる初心者向けの大会を6つ厳選してご紹介します。 初心者向けトレイルラン大会の定義 本記事では、以下の基準を「初心者向け」として定義しています。 【初心者向けの5つの基準】 ❶距離:25km以下平地のハーフマラソンを完走できる体力があれば挑戦可能な距離設定。トレイルはロードより負荷が高いため、まずは短めの距離から始めるのが安全です。 ❷累積標高:2,000m以下累積標高が低いほど、アップダウンが少なく体力的な負担が軽減されます。初心者には1,500m前後までが適切で、ハイキング経験があれば十分対応可能です。 ❸制限時間:5時間以上歩きを交えながらでも完走できる余裕のある制限時間設定。初めてのトレイルでは予想以上に時間がかかるため、ゆとりのある時間設定が重要です。 ❹コース整備:登山道が整備されている明確な道標があり、迷いにくい整備されたコース。初心者でも安心して走れる環境が整っています。 ❺アクセス:公共交通機関で行きやすい駅からのアクセスが良好、またはシャトルバスが運行されている大会。疲労後の移動も考慮した利便性が重要です。 これらの基準は、トレイルラン初心者が「完走の達成感」を味わいながら、安全に楽しめる環境を重視して設定しています。 東海地方の初心者向けトレイルラン大会6選 1. 犬山MOMOTAROトレイルランニングレース 開催日時: 2026年1月31日(土)・2月1日(日) 開催場所: 愛知県犬山市栗栖小学校周辺 距離・累積標高: ラン&ウォーク10km級(累積標高未公表)/ロング17km級(制限時間6時間) 参加人数: 100〜499名 駐車場: 情報未公表(公共交通機関利用推奨) レースの特徴・魅力: 桃太郎伝説の地・犬山で開催される里山トレイル。 木漏れ日と川のせせらぎを感じながら走れる初心者に優しいコース設計で、キッズレースも同時開催されるファミリー向けの大会です。 初心者にオススメな点: 10km級のラン&ウォーク部門は制限時間5時間で、歩きを交えながら完走を目指せる設計。 小学生から参加可能で、家族や仲間と一緒に楽しめる温かい雰囲気が魅力です。 公式URL: https://inuyama-momotaro-trail.com/ 2. DA...
【2026年最新版】初心者も完走しやすいトレイルラン大会(東海地方版) 6選
こんにちはOLENOです。 2026年、トレイルランニングに初めて挑戦したいけれど、「完走できるか不安」「どの大会を選べばいいかわからない」と悩んでいませんか? 東海地方には、初心者でも安心して...

【2026年最新版】トレラン初心者必見!完走しやすい関西のトレイルランニング大会10選
「トレラン初心者だけど大会に出てみたい」「初めてのトレランはどの大会が安心?」 そんな方に向けて、2026年に関西で開催される完走しやすいトレイルラン大会を厳選してご紹介します。 関西は都市近郊に里山が多く、アクセスが良いトレラン大会おすすめエリア。 本記事では、初心者が不安なく参加できる大会だけをピックアップしています。 初心者向けトレイルラン大会の定義 本記事では、以下5つの基準を満たす大会を初心者向けトレイルラン大会と定義します。 初心者向け5つの基準 ❶距離:25km以下トレイルはロードより負荷が高いため、まずはハーフマラソン前後が安全。 ❷累積標高:2,000m以下1,500m前後までならハイキング経験があれば十分対応可能。 ❸制限時間:5時間以上歩きを交えても完走でき、焦らず進める設定。 ❹整備された登山道中心岩場や鎖場が少なく、安全性が高い。 ❺公共交通機関でアクセス可能初大会は車不要がベスト。疲労後も安心です。 【関西版】トレラン初心者におすすめの大会10選(2026年) 1. 第23回 生駒トレイルラン<冬山> 開催日時: 2026年1月24日(土) 開催場所: 大阪府~奈良県(生駒山系)スタート:私市水辺プラザ(京阪私市駅より徒歩5分)ゴール:24km部門は枚岡梅林(近鉄枚岡駅より徒歩約2分) 距離・累積標高: 24kmコース:約24km / 累積標高700m 29kmコース:約29km / 累積標高975m 参加人数: 各コース300名(定員)...
【2026年最新版】トレラン初心者必見!完走しやすい関西のトレイルランニング大会10選
「トレラン初心者だけど大会に出てみたい」「初めてのトレランはどの大会が安心?」 そんな方に向けて、2026年に関西で開催される完走しやすいトレイルラン大会を厳選してご紹介します。 関西は都...

初心者が知っておきたい「第1回 奈良ウルトラマラソン」の全貌〜時を駆ける100kmの旅へようこそ〜
奈良ウルトラマラソンのコースが公開! ついに発表されました。 2026年5月、奈良県で初開催となる奈良ウルトラマラソン(100km)。 コース詳細を見た瞬間、思わず「これはすごい」と声が出ました。 コース詳細はこちら スタートは藤原宮跡。そこから飛鳥、吉野金峯山寺、そして古代遺跡や世界遺産候補地を抜ける、まさに“奈良の文化と自然を丸ごと駆け抜ける旅”。 今回は、初めてウルトラマラソンに挑む人、そして奈良南部に来られたことが無い方にとって、楽しめるポイントと大変なポイント、そしてこの大会の「本当の楽しさ」をお伝えします。 コース解説:初心者が楽しめるポイント&大変なポイント ※以下の内容は、公開されている全体マップと大会情報をもとにした予測です。詳細なコース図や関門情報は現在準備中とのことですので、正式発表をお待ちください。実際のコース状況は異なる可能性があります。 【序盤 0-30km】藤原宮跡→明日香村 楽しめるポイント 朝焼けに染まる大和三山の絶景: スタート直後、朝の静けさの中で、大和三山(耳成山・畝傍山・香久山)を望む感動的なシーンから始まります 飛鳥の古墳群: 高松塚古墳、石舞台古墳など、教科書で見た歴史遺産を走りながら体感できます 比較的フラットな道: まだ体力も十分で、古代の風景を楽しむ余裕があります 大変なポイント オーバーペースに注意: テンションが上がって飛ばしすぎると、後半に響きます。「まだ序の口」と自分に言い聞かせて、我慢の走りを心がけましょう 【中盤前半 30-50km】壺阪峠への挑戦 大変なポイント 標高300mの壺阪峠: この大会最大の難関といえるアップダウン。初心者は無理せず歩きを入れるのが完走のコツです ...
初心者が知っておきたい「第1回 奈良ウルトラマラソン」の全貌〜時を駆ける100kmの旅へようこそ〜
奈良ウルトラマラソンのコースが公開! ついに発表されました。 2026年5月、奈良県で初開催となる奈良ウルトラマラソン(100km)。 コース詳細を見た瞬間、思わず「これはすごい」と声が出ました...

【レースレポート】背水の陣で挑んだ信越五岳トレイルランニングレース2025 110K(後編)
前編の内容はこちらから 笹ヶ峰〜戸隠:おやぶんトレイン と カフェイン抜きの効果! 笹ヶ峰に到着すると多くの知り合いから激励をいただき少しメンタル回復。サポートエリアでは関西メンバーから「イケるイケる」と声をかけてもらい嬉しかったのですが、Aプランと息巻いていたのにBプランすら押している不甲斐なさに涙が出そうになりましたが、「泣くのはゴールしてから!」と言い聞かせ、ぐっと堪えます。 ここでは、雑炊に梅チューブの組み合わせをいただく。胃腸トラブルがないのが唯一の救い。Tシャツを着替え、夜パートに向けて準備。過去2回は大雨の笹ヶ峰だったので、芝生の上でサポートを受けられたのが新鮮でした。トイレで尿の色が通常に戻っているのを確認でき一安心。 ここからは、途中下車が許されない(笑)おやぶんトレインに乗車です。 ペーサー:「調子はどうですか?走れますか?」 私:「膝が痛くなっているので、下りがしんどいです」 ペーサー:「では、走れるところは走って無理せず行きましょう」 そう簡単に、歩かせてくれません笑 ひたすら離れないように必死で付いていき、西登山道入り口へ。 ここでBプラン5分押しまで詰めることができました。さすがです! ここから先の極悪トレイルは、過去2回で免疫ができていたのか、開き直って泥の中を進みます。登りはキツくないかも?と思えましたが、その分下りで抜き返され、結果イーブンペースに…。 Bプラン7分押しで大橋林道に到着。 大橋林道のエイドでは、3週間我慢していたカフェインを摂取!コーラとチップスターのジャンクセットに舌鼓を打ち、エイドアウト。 昨年はこの区間で眠気が出て辛かったが、カフェイン抜きの効果なのか、カフェイン入りのジェルとコーラで覚醒し笑、淡々と進み続け戸隠に到着。 Bプラン12分押しで戸隠に到着… 戸隠〜ゴール:ロキソの呪文と歓喜の瞬間 戸隠でも雑炊に梅チューブ、そして楽しみにしていたマッハコーヒーをいただく。カフェイン抜きしていた体にはガンギマリ(個人差あり笑)で極上の美味さでした。...
【レースレポート】背水の陣で挑んだ信越五岳トレイルランニングレース2025 110K(後編)
前編の内容はこちらから 笹ヶ峰〜戸隠:おやぶんトレイン と カフェイン抜きの効果! 笹ヶ峰に到着すると多くの知り合いから激励をいただき少しメンタル回復。サポートエリアでは関西メンバーから「...

【レースレポート】背水の陣で挑んだ信越五岳トレイルランニングレース2025 110K(前編)
いつぶりの、ブログ更新なんでしょうか…開発担当 のーまるです汗 昨年、悪天候のため特別完走となった信越五岳110K。石川弘樹さんの粋な計らいでいただいた優先エントリー権を胸に、今年もスタートラインに立たせていただきました。 昨年の記事はこちらから 信越五岳トレイルランニングレース2024 110K(前編) 信越五岳トレイルランニングレース2024 110K(後編) 「今年こそ、何としてもゴールゲートをくぐる!」 3度目の正直となる今回のチャレンジは、昨年もお世話になったペーサーに加え、サポートもお願いして背水の陣で挑みます! 最強のペーサー&最高のサポーター 設定したプランは以下の通り。 ・Aプラン: 20時間ペース ・Bプラン: 21時間ペース ・Cプラン: 時間内完走 さあ、完走できるのか!?不安と期待が入り混じる中、信越五岳110Kが始まりました。 スタート〜バンフ:想定外のスリッピーな難コース スタート5分前。雨脚は強まる一方…...
【レースレポート】背水の陣で挑んだ信越五岳トレイルランニングレース2025 110K(前編)
いつぶりの、ブログ更新なんでしょうか…開発担当 のーまるです汗 昨年、悪天候のため特別完走となった信越五岳110K。石川弘樹さんの粋な計らいでいただいた優先エントリー権を胸に、今年もスタート...

【2026/05開催】奈良でウルトラマラソンが開催決定!過去の開催地と比較してみた
【目次】 ・奈良でウルトラマラソンが開催決定 ・サロマ湖・四万十川・飛騨高山…国内の有名大会 ・奈良開催のウルトラは何が違うのか? ・ランナー視点からの期待と課題 ・奈良から広がる新しいランニングカルチャー ・奈良と靴下、そして私たちOLENOの想い ・まとめ 奈良でウルトラマラソンが開催決定 2026年5月、奈良県南部を舞台にした100kmウルトラマラソンの開催が決定しました。奈良県出身者としては非常に嬉しく思います。 スタートは橿原市から、吉野金峯山寺や古代遺跡を巡り、世界遺産候補地を背景に駆け抜けるという壮大なコース。参加枠は3,000名に限定され、国内外から多くのランナーが集結することが期待されています。 「歴史と文化を走る100km」というコンセプトは、これまでの国内ウルトラマラソンにはなかった新しい切り口です。 ここでは、奈良での大会の特徴を整理しながら、過去に全国各地で開催されてきた有名ウルトラマラソンと比較し、その魅力と可能性を探ってみたいと思います。 サロマ湖・四万十川・飛騨高山…国内の有名大会 サロマ湖100kmウルトラマラソン(北海道) 1986年にスタートした、日本を代表する100kmレース。国内外から2,000名以上のランナーが集う歴史ある大会です。 最大の特徴は、サロマ湖畔をひたすら走るフラットなコース。気温が低い年は走りやすい反面、風が強かったり、真夏日に近い暑さになることもあり、気象条件に大きく左右されるのが難しさでもあります。 世界記録が誕生した大会としても知られ、エリートランナーから市民ランナーまで幅広い層に愛されています。 四万十川ウルトラマラソン(高知) 高知県の清流・四万十川を舞台にした大会。美しい自然と地元住民の温かい応援が大きな魅力です。 走力勝負というよりは、「いかに自然と一体となって楽しめるか」が問われるレース。補給所では地元特産の食べ物が並び、「食を楽しむウルトラマラソン」としても人気です 参加者は抽選制で、毎年数倍の応募倍率を誇ります。 飛騨高山ウルトラマラソン(岐阜) 古い町並みと山岳地帯を駆け抜ける100km。累積標高は2,500m以上と、国内屈指のアップダウンを誇る「山岳型ウルトラ」です。 町並みを走り抜ける景観美と、激しい高低差に挑むタフさが共存。まさに“己との戦い”という色が強い大会です。 ...
【2026/05開催】奈良でウルトラマラソンが開催決定!過去の開催地と比較してみた
【目次】 ・奈良でウルトラマラソンが開催決定 ・サロマ湖・四万十川・飛騨高山…国内の有名大会 ・奈良開催のウルトラは何が違うのか? ・ランナー視点からの期待と課題 ・奈良から広がる新しいランニン...

登山靴は進化したのに、登山靴下は取り残されていないか?
【目次】 1.登山愛好家との対話から見えた“違和感” 2.登山靴の進化:重い革靴から、軽量・高性能ブーツへ 3.厚手メリノウール靴下のデメリット(靴が進化したからこそ生まれる問題) 4.厚手メリノウール靴下に頼りすぎると起きやすい症状 5.靴と同じように、靴下も“シーン別”で選ぶ時代 6.「お店の常識=正解」ではない 7.まとめ:靴下も進化させるべき装備 登山愛好家との対話から見えた“違和感” 「登山靴はどんどん進化しているのに、靴下は昔からあまり変わっていない気がするんです。」 これは、年間60回以上山に登る愛好家の方と話していて出てきた言葉です。 彼は長年さまざまな靴と靴下を試してきましたが、強く感じているのは 「靴と靴下の進化スピードの差」 です。 確かに登山靴は、ここ数十年で大きく進化しました。 昔は重く硬い革靴が主流で、靴底に釘を打っただけのシンプルな構造。長時間歩けば足は痛み、濡れたら乾かず、冷えから守るのも厚手の靴下に頼るしかありませんでした。 しかし現代の登山靴は違います。 ゴアテックスなどの防水透湿素材を用い、EVAやPUフォームのミッドソールでクッション性を高め、軽量化とフィット感を両立。 さらに厳冬期の断熱性を備えたブーツや、夏山や縦走に適した薄くて軽い靴まで、シーンごとに選べる豊富なバリエーションが存在します。 では、靴下はどうでしょうか。 「メリノウール」「厚手」だけで本当にいいのか? 登山靴下といえば、売り場でよく目にするのが 「メリノウール」「厚手」 というキーワードです。 メリノウールは調湿性・保温性・防臭性に優れ、登山に最適な素材であることは間違いありません。 厚手の靴下も、長時間の登山で足裏を守るクッションとして重要な役割を果たします。 ...
登山靴は進化したのに、登山靴下は取り残されていないか?
【目次】 1.登山愛好家との対話から見えた“違和感” 2.登山靴の進化:重い革靴から、軽量・高性能ブーツへ 3.厚手メリノウール靴下のデメリット(靴が進化したからこそ生まれる問題) 4.厚手メリ...

足トラブルとアーチサポートソックス ― ランナーが長く走り続けるために
こんにちは。 1. はじめに ― ランナーの足は過酷な環境にさらされている ランニングを続けていると、多くの人が「足の裏が痛む」「後半になると踏ん張りが効かない」「走った後に土踏まずがジンジンする」といった違和感を経験します。特に長距離やトレイルでは、足裏への負担が積み重なり、走る楽しさを奪ってしまうことさえあります。 これらは病気ではなく、ランニングという繰り返し動作の中で足の機能が追い込まれた結果にすぎません。 とはいえ、その小さな違和感を軽視すると、怪我やモチベーション低下につながりかねません。だからこそ、日常的にできる対策が重要になります。 2. 足裏のアーチ ― ランナーを支えるサスペンション 足裏には「アーチ」と呼ばれる構造があります。 母趾球・小趾球・かかとの三点(フットトライポッド)で支え、着地でアーチが沈み込み衝撃を吸収。中間局面では足底腱膜がバネのように張力を蓄え、母趾が反り上がる(ウィンドラス機構)ことでその力を蹴り出しへと再利用します。 この一連の働きはまるでサスペンション。スムーズに走るための「受け止める → 貯める → 返す」という連鎖が、ランナーの一歩一歩を支えています。 3. アーチが崩れると何が起きるのか ところが、長距離や不整地で走ると、アーチの働きが乱れることがあります。 ・アーチが沈み込みすぎる → 足裏の一点に負担が集中して痛みが出やすい ・接地が安定せず、膝や股関節まで余計なブレが波及する ・足の反発をうまく活かせず、後半にフォームが崩れる 「足裏が痛い」「疲れがたまる」「踏ん張りが効かない」という感覚の背景には、こうしたアーチの乱れが関係している場合があります。...
足トラブルとアーチサポートソックス ― ランナーが長く走り続けるために
こんにちは。 1. はじめに ― ランナーの足は過酷な環境にさらされている ランニングを続けていると、多くの人が「足の裏が痛む」「後半になると踏ん張りが効かない」「走った後に土踏まずがジンジン...

アーチサポートソックスで走りが変わる!パフォーマンスを支える足元の新常識
【目次】 1.ランナーやトレーニーに多い足の悩み 2.アーチの安定がパフォーマンスを左右する理由 3.アーチサポートソックスの効果 4.開発者が悩んだ「サポート量」のさじ加減 5.インソールではなくソックスで支えるメリット 6.まとめ 1. ランナーやトレーニーに多い足の悩み 長距離ランニングやハードなトレーニングを続けると、どうしても足裏やふくらはぎに疲労が溜まってきます。 ・30kmを超えると足裏が痛む ・ふくらはぎがパンパンに張る ・マメや水ぶくれができやすい ・フォームが崩れて膝や腰に違和感が出る これらの症状の背景には、足裏のアーチの崩れが潜んでいます。 アーチが機能していれば着地衝撃を吸収し、エネルギーを効率的に次の一歩へとつなげられます。 ですが、アーチが落ちると衝撃がダイレクトに骨や筋肉へ伝わり、疲労や怪我につながってしまうのです。 2. アーチの安定がパフォーマンスを左右する理由 アーチは“受け止める・貯める・返す”を担う足のサスペンションです。 専門的なお話ですが、 着地直後、足は母趾球・小趾球・かかとの三点(フットトライポッド)で地面を捉え、アーチがわずかに沈んで衝撃を吸収します。 中間局面では足底腱膜や周囲筋がバネのように張力を蓄え、蹴り出しで母趾が反り上がる(ウィンドラス機構)と、その張力が再利用され推進効率を高めます。これが「受け止める→貯める→返す」の連鎖です。 アーチが落ちていると、この連鎖が崩れます。沈み込みが深くなり、接地のたびに脛骨の過内旋や膝の内側への崩れが起きやすく、股関節までブレが波及。 結果として ・接地時間がわずかに伸び、ピッチが乱れやすい...
アーチサポートソックスで走りが変わる!パフォーマンスを支える足元の新常識
【目次】 1.ランナーやトレーニーに多い足の悩み 2.アーチの安定がパフォーマンスを左右する理由 3.アーチサポートソックスの効果 4.開発者が悩んだ「サポート量」のさじ加減 5.インソールでは...

毎日の疲れを軽減!アーチサポートソックスが“立ち仕事の味方”になる理由
【目次】 1. 立ち仕事・歩き仕事で足が悲鳴を上げる理由 2. アーチサポートソックスとは? 3. 日常生活で感じるメリット 4. インソールとの違い 5. OLENOのアーチサポートソックス ― Comod(y)シリーズ 6. こんな人にこそ選んでほしい 7.まとめ 1. 立ち仕事・歩き仕事で足が悲鳴を上げる理由 一日中立ちっぱなし、あるいは接客や営業で歩きっぱなし…。 「夕方になると足がパンパンにむくむ」「かかとがジンジン痛む」そんな経験をしたことはございませんか? このような疲労の大きな原因の一つが、足裏のアーチ(土踏まず)の崩れです。 人間の足裏には3つのアーチ(内側縦アーチ・外側縦アーチ・横アーチ)が存在し、衝撃吸収や体重分散といった大切な役割を担っています。 しかし、長時間の立ちや歩行でアーチが支えを失うと、足裏に過剰な負担がかかり、疲労や痛みが蓄積していくのです。 現代人は運動不足や柔らかすぎる靴の影響でアーチが弱くなりがち。 その結果、偏平足や足底筋膜炎、さらには姿勢の崩れや腰痛につながるケースも少なくありません。 ※偏平足:足のアーチ構造が崩れて土踏まずが平らになった状態。 ※足底腱膜炎:足裏のアーチを支える「足底腱膜」が炎症し、かかと周辺に痛みが生じる疾患。...
毎日の疲れを軽減!アーチサポートソックスが“立ち仕事の味方”になる理由
【目次】 1. 立ち仕事・歩き仕事で足が悲鳴を上げる理由 2. アーチサポートソックスとは? 3. 日常生活で感じるメリット 4. インソールとの違い 5. OLENOのアーチサポートソックス ...

【ウールが1番?】「冷えは足元から」の本当の意味と、冬用靴下の選び方
【目次】 1.「冷えは万病のもと」は本当か? 2.足元から体温をコントロールするメカニズム 3.冬用靴下の選び方完全ガイド 4.“重ね履き”は効果的?それとも迷信? 5.まとめ 1. 「冷えは万病のもと」は本当か? 冬になるとよく耳にする「冷えは万病のもと」という言葉。これは単なる迷信ではなく、現代医学や東洋医学においても、冷えが体調不良の引き金となることは明確にされています。 とくに注目したいのが“足元の冷え”です。足は心臓からもっとも遠く、血流が滞りやすい部位。さらに、皮下脂肪が少ないため体温を維持しにくく、冷えやすい構造になっています。 足元が冷えると、身体は体温を逃がさないように毛細血管を収縮させ、さらに血流が悪化。これにより、次のような症状が引き起こされやすくなります: ●免疫力の低下(風邪をひきやすくなる) ●内臓機能の低下(胃腸が冷えて便秘や食欲不振) ●自律神経の乱れ(不眠や頭痛) ●精神的な不安定(冷えによるイライラ) 「ただ足が冷えるだけ」と思いがちですが、実は体全体のバランスを崩す原因になりうるのです。 2. 足元から体温をコントロールするメカニズム 体温の約30%が足裏から失われているというデータもあるほど、足元は“熱の出入り口”です。とくに足裏には多くの動静脈吻合(AVA)という血管構造が存在し、ここが開閉することで体温の調整が行われています。 寒いと感じると、このAVAが閉じ、体内の熱を逃がさないようになります。ですが、末端冷え性の方や自律神経が乱れている方は、この調整がうまくいかず「足が冷え切って戻らない」状態になります。 こうした場合、物理的に足を保温し冷気から守ることでAVAの過度な閉鎖を防ぎ、全身の体温コントロールがしやすくなるのです。 つまり、適切な靴下を履くことは、単に足を温めるだけではなく、身体の“サーモスタット”を正常に働かせるための重要な手段でもあるのです。 3. 冬用靴下の選び方完全ガイド 冬の靴下選びで重要なのは、保温性・吸湿性・フィット感・通気性のバランスです。以下に代表的な素材の特徴を紹介します: ■ メリノウール ...
【ウールが1番?】「冷えは足元から」の本当の意味と、冬用靴下の選び方
【目次】 1.「冷えは万病のもと」は本当か? 2.足元から体温をコントロールするメカニズム 3.冬用靴下の選び方完全ガイド 4.“重ね履き”は効果的?それとも迷信? 5.まとめ 1. 「冷え...

【夏・冬】アームスリーブで変わる登山体験:機能性・快適性のベストバランス
登山は、季節を問わず自然の魅力を五感で感じられる貴重なアクティビティ。特に夏山では爽やかな緑の中を歩く気持ちよさが格別ですが、その一方で、強い紫外線や発汗への対策が必要です。逆に冬山では、冷気や雪による肌の冷えを防ぐ装備が欠かせません。 そうした気候条件に対応するのが「アームスリーブ」。一見地味な存在ですが、実は登山装備の中でも非常に実用性の高いアイテムです。本記事では、登山用アームスリーブに求められる条件と、最適解として紹介したいアームスリーブについてお話させていただきます。 【目次】 1.登山でのアームスリーブに求めること 2.スポーツ向けかファッション向けか?選ぶ際のポイント 3.最適解は「お手頃価格 × 信頼性 × ファッション性」 4.OLENOのアームスリーブが登山に適している理由 5.登山ユースユーザーからの口コミ 6.まとめ:アームスリーブは登山装備の一部として再注目を 1.登山でのアームスリーブに求めること アームスリーブは季節や気候、登山スタイルによって多様な役割を果たします。 ①紫外線・日焼け対策(特に夏山) 標高が高くなるにつれて紫外線量は増加します。夏山では日差しが特に強く、長時間の登山では日焼けが深刻なダメージに。日焼け止めでは汗で流れてしまうこともあるため、物理的に肌を守れるアームスリーブは非常に有効です。 なお、私見ではありますが、長袖シャツよりもアームスリーブを推奨する理由として、長袖は暑さを感じやすく、特に登山中の気温変化や運動強度に応じた温度調整が難しいと感じるからです。半袖+アームスリーブの組み合わせであれば、必要に応じて着脱できる柔軟性があり、登山中の快適さを保ちやすいと考えています。 ②寒暖差への対応(特に冬山) 朝晩の冷え込みが厳しい冬山や、風が強い稜線では、肌の露出が大きな冷えの原因になります。アームスリーブがあれば、冷却されすぎるのを防ぎつつ、保温効果も確保できるため、防寒対策の一環としても非常に有効です。 ③汗・蒸れ対策と冷却効果 登山中は大量の汗をかくため、吸汗速乾性は欠かせません。最近のアームスリーブには、汗をすばやく吸収し、外気に触れることで気化熱を利用して体表の温度を下げる設計が施されたものもあります。この気化熱による冷却効果が、夏山においては特に「涼しい着用感」につながります。 ④摩擦や虫刺され防止 藪や岩場などでの擦り傷防止、また虫刺されからの保護としてもアームスリーブは活躍します。半袖+アームスリーブというスタイルなら、気温に応じて着脱できるため、一日を通じて快適に過ごせます。 2.スポーツ向けかファッション向けか?選ぶ際のポイント...
【夏・冬】アームスリーブで変わる登山体験:機能性・快適性のベストバランス
登山は、季節を問わず自然の魅力を五感で感じられる貴重なアクティビティ。特に夏山では爽やかな緑の中を歩く気持ちよさが格別ですが、その一方で、強い紫外線や発汗への対策が必要です。逆に冬山では、冷気や...

【足の臭い対策】もう悩まない!“靴下選び”でニオイを抑える方法
「足、クサくない?」――それ、靴下で変わります 仕事終わりに靴を脱ぐ瞬間。 ランニング後にシューズを脱いだとき。 ふと自分の足の臭いが気になった経験はございませんか? 実は足のニオイは、靴下の選び方で大きく変わります。消臭スプレーや足用ソープも効果的ですが、毎日身につける靴下こそが“本丸”。 この記事では、足の臭いの原因から、素材別の対策ソックス、洗濯のコツまで、まるっと解説します。 【目次】 1. 足の臭いの正体は「汗」じゃない? 2. 足の臭いを抑える靴下の3条件|“素材より大切”な基本設計 3. 素材別|臭い対策に効果的な靴下とは? 4. 洗い方でも差が出る?実は“臭い戻り”の原因に 5. 足の臭い対策、靴下だけで9割変わる 6. OLENOのおすすめ防臭・吸汗ソックスをご紹介 1. 足の臭いの正体は「汗」じゃない? まず理解しておきたいのは、汗自体に臭いはないということ。問題なのは、汗を吸わずに靴内に残ったままの状態です。 足のニオイの主な原因は以下の3つ。 ・足裏に集中する汗腺から出る大量の汗 ・湿った環境で繁殖した雑菌 ・雑菌が皮脂や角質を分解して発生する「イソ吉草酸」というニオイ成分 つまり、“蒸れて濡れたまま”の状態が続くほど、ニオイは強くなります。 ...
【足の臭い対策】もう悩まない!“靴下選び”でニオイを抑える方法
「足、クサくない?」――それ、靴下で変わります 仕事終わりに靴を脱ぐ瞬間。 ランニング後にシューズを脱いだとき。 ふと自分の足の臭いが気になった経験はございませんか? 実は足のニオイは、靴下の...

ランニングソックスがすぐダメになる原因は“洗濯”だった?NG行動と長持ちのコツを解説
原因は“洗い方”にあるかもしれません お気に入りのランニングソックス。まだ数回しか履いていないのに「なんだか伸びてきた」「サポート感が弱くなった」「型崩れしてきた…。」 その違和感、実は「洗い方」や「干し方」など日常の扱い方が原因かもしれません。 近年のランニングソックスは、タフな素材・高機能設計で長持ちするよう作られています。ですが、意外と差が出るのが「洗濯」の部分。扱い方ひとつで寿命も機能性も大きく変わるのです。 この記事では、やりがちなNG行動とその理由、そして長持ちさせる洗濯の基本ルールを詳しく解説します。 【目次】 1. ランニングソックスの寿命を縮める“洗濯NG行動” 2. 高機能でも“洗い方次第”で差が出る 3. 正しい洗濯で寿命を延ばす!5つのルール まとめ 1. ランニングソックスの寿命を縮める“洗濯NG行動” ■ NG①:洗濯ネットに入れずそのまま洗う 他の衣類と擦れ合い、摩耗や型崩れ、糸のヨレが発生。特に高機能ソックスは繊細な構造のため、ネットなしはリスク大。 ■ NG②:柔軟剤を使う 柔軟剤の陽イオン界面活性剤が繊維をコーティングし、 ・吸水性の低下 ・速乾性の阻害 ・防臭加工への干渉 など、本来の機能性を著しく損なう可能性があります。 特に、メリノウールや吸汗速乾素材との相性は最悪。「ムレやすくなった」と感じたら、柔軟剤を疑ってみてください。 ■ NG③:乾燥機や直射日光での乾燥...
ランニングソックスがすぐダメになる原因は“洗濯”だった?NG行動と長持ちのコツを解説
原因は“洗い方”にあるかもしれません お気に入りのランニングソックス。まだ数回しか履いていないのに「なんだか伸びてきた」「サポート感が弱くなった」「型崩れしてきた…。」 その違和感、実は「洗い方...

夏ランの汗・雨ランの濡れ!濡れても快適なランニングソックスの選び方
夏のランニング、足元が不快じゃないですか? 「走っていると足が蒸れる」「汗や雨で靴の中がびしょびしょ」「濡れると靴擦れする」――そんな悩み、夏ランナーあるあるです。特に梅雨〜真夏の季節は、気温・湿度ともに高く、足元の環境は過酷そのもの。 たまに経験する“雨ラン”対策においても大きな差が出ます。 そこで本記事では、「濡れても快適」に注目し、初心者でも実践できる視点で、夏や雨の日のランニングでも頼れるソックスの選び方を、素材・構造・形状の3つの視点から解説します。 【目次】 1. 濡れても快適なソックスとは?カギは「素材」 2. ソックスの構造も、快適さの鍵 3. 濡れても快適な形状はどれ? 4. 実体験レビュー:雨の日ランで分かった違い 5. まとめ 1. 濡れても快適なソックスとは?カギは「素材」 夏や雨の日のランニングでは、ソックスが汗や水に濡れるのは正直避けることができません。 防水ソックスというのも実はございますが、ランニングに耐えうる耐久性は持ち合わせていないものが多く、高い値段(5,000円以上)で買ってすぐにダメになった(浸水するようになり、ただの分厚い靴下になった)という声は多いそうです。 だからこそ重要なのは、「濡れても不快にならない素材」を選ぶこと。特に真夏は不快感が倍増します。 ここでは夏に向いている代表的な3つの素材を、順に紹介します。 ■ 速乾&軽量重視なら:高機能化繊(ポリエステル・ナイロンなど) まず、最速で乾かしたい人に最適なのが高機能化繊。 代表されるポリエステルやナイロンなどの合成繊維は、汗をかいてもすぐに乾き、ベタつきを最小限に抑えてくれます。軽さを重視されたい方はこれが特におすすめ。 ●ポリエステル:吸汗・速乾性が高く、ムレにくい ●ナイロン:摩耗に強く、耐久性も高い →雨や汗によるダメージが心配な方にはおすすめの素材濡れてもいい靴下として理想的な特性...
夏ランの汗・雨ランの濡れ!濡れても快適なランニングソックスの選び方
夏のランニング、足元が不快じゃないですか? 「走っていると足が蒸れる」「汗や雨で靴の中がびしょびしょ」「濡れると靴擦れする」――そんな悩み、夏ランナーあるあるです。特に梅雨〜真夏の季節は、気温...