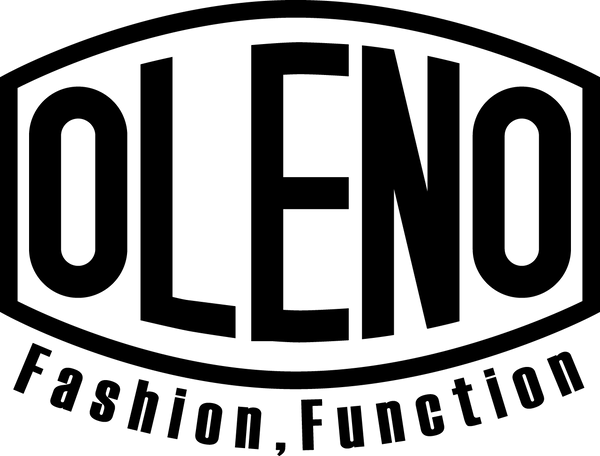最近、チョコザップなど気軽に通えるジムが登場したおかげで、ダイエットや健康維持のためにランニングをし始めた方も多いのではないでしょうか?
そういった方々を見ていて思うのですが、服や靴には気を使い、良いものを身に着けているのですが、靴下は、(言い方が悪くなりますが、、)こだわらない方が多い印象です。

それもそのはず、靴下は、あくまで靴を履く際に身に着けておかないといけないものという認識しかされておらず、「こだわる必要性がない」と思われてしまっているからなのかと思います。(ユニクロやGUがとりあえず履けて、デザインもよく・安価な靴下を販売し、最近では、コンビニもコスパの良い靴下を販売しているので、そうなるのも仕方がないですが、、)
ただ、ランニングやスポーツに限って言えば、普段の生活の何倍も足への負担が増え、対策をしっかりしておかないと、怪我やトラブルの元になってしまいます。(かかとの靴擦れや足裏のマメ、足が蒸れるのも靴下から起きるトラブルの一つ)
今回はランニングソックスに必要な機能について、競技者であり生産者として、ダブルの視点でお話させていただきます。ランニング中の足のトラブルに悩まれている方や今後ランニングを始めようとされる方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
足の蒸れを防ぐ、吸水性と速乾性

ランニングに限らず、夏場に外出をして帰宅した際に足が蒸れている。そして「嫌な臭いがする、、、」といった経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
足が蒸れてしまうのは、足から出た汗や水分が
・吸水されずにそのまま滞留している(吸水性が低い)
・吸水はされるが、水分が蒸発されない or 湿気が放出されずに湿度が高くなっている( 速乾性が低い or 放湿性が低い)
からです。

なので吸水性と速乾性の両方を確保できる靴下を履けばいいのですが、現実はそうはうまくいきません。
靴下に使われる繊維たちにはそれぞれ特徴があり、Aを求めるとBが弱くなる。Bを求めるとAが弱くなるといったように、融通が利かない場合が多いです。
例えば、吸水性が非常に高い繊維だと、綿(コットン)やウールがありますが、綿(コットン)の場合は速乾性が非常に低く、ウールの場合は耐久性が非常に低いためランニングソックスには不向きとなります。
逆に、速乾性の高いポリエステルの場合、耐久性も強くなっていますが、吸水性が低く惜しい性能になっています。(ただ、速乾性が高いので、ある程度の水分量であればすぐに吸水されずとも、蒸発していくため他の素材よりは蒸れにくい)
ただ最近では、これらの繊維をうまく組み合わせて速乾性や吸水性を高めつつ、しっかり耐久力もあるといったハイブリットなランニングソックスが出てきているので一度探してみるといいかもしれません。

↑ 従来のポリエステルとはちがい、断面図が上記のように特殊な形をしています。(通常は丸い形をしている)この特殊な断面のおかけで凹凸が生まれ、その凹凸に水分が入っていくことができ(吸水)、吸水された水分はそのまま蒸発されていきます。(速乾)
当社OLENOでも、独自の特殊素材によりハイブリッドなランニングソックスを取り扱っております。
遂に完成した特殊素材!足が蒸れないランニング用ソックス「アルティメット SHR」
破れにくさ(耐摩耗性)
吸水性・速乾性以外にランニングソックスに求められる機能としては、破れにくさです。

耐久性も吸水性・速乾性と同じで、基本的には繊維が本来持つ耐久性に依存しており、ポリエステルやアクリルは耐久性が高いですが、ウールや綿(コットン)は耐久性が低くなっております。
そのため、破れにくい靴下を求める方はウールや綿をベースに作っている靴下は避けるほうがいいです。
実は一つ注意しておかないといけないのが、そもそも、耐久性が高い靴下を着用していても破れる人は破れてしまいます。
同じ身長、同じ体重、同じ靴のサイズでも、人それぞれ足の形や指の長さ、形が異なっており、すべての人にぴったり合う靴下は存在しません。繊維の編み方次第では「あの人は破れにくい」けど、「この人は破れやすい」といったことがどうしても起きてしまいます。また、靴のサイズが全然合っていないや走り方が悪い場合も、靴下が破れやすい原因になってしまいます。
なので素材が強いのは大前提で、根気よく自分の足の形にあった靴下を探す必要があるかもしれません。当社ではランニングの中でも、最も過酷とされているトレイルランニングソックスを作っているため、非常に耐久性が高い素材を使って靴下を開発しています。一度お試しいただいてもいいかもしれません。
軍用装備に使われる超耐久の繊維を使用したランニング用ソックス「アルティメット ASO」
足の疲れを緩和する着圧(加圧)性

続いては着圧です。ここは正直好き嫌いが分かれる部分にはなりますが、あくまでランニングソックスの機能としては、着圧はあったほうがベターかと思います。
着圧をすることで、血管が締まり血液の流れがよくなります。そうすることで疲労などが溜まりにくい、むくみ解消といったメリットがありますが、締め付けがきつくなりすぎたり、長時間着用していると、痛みや締め付けが不快感に代わってしまったりします。(フルマラソンぐらいの距離であれば特に問題はないでしょう)
そのため、もともと着圧が苦手な方や一日中ずっと履く方は、着圧が少ないランニングソックスを選ぶのをおすすめします。
市民ランナーと半年かけて開発したプロ仕様のランニングソックス
将来の足の形に関わる、アーチサポート機能
最後はアーチサポート機能です。
アーチとは足のかかと、親指の付け根、小指の付け根の3点を結んだラインのことを言います。

アーチが合わない靴を履いていると、疲れやすく、最悪の場合アーチが崩れてしまうこともあります。
アーチサポート機能は、足裏のアーチを支えることに特化した機能になるため、アーチが崩れることへの予防として注目されています。

アーチサポートについては詳しく紹介していますので、気になる方は是非ご覧ください。
以上、ランニング用ソックスに必要な機能を紹介させていただきました。今回挙げた機能以外にも保温性や消臭性、防菌性といった機能も重要視されることがありましたが、普段使う靴下にも必要な機能なので、別の記事で紹介させていただきます。
たかが靴下、されど靴下。
靴よりも一番足に近いからこそ、靴下にもこだわってみてはいかがでしょうか?